散乱を扱う場合、波動関数よりもむしろ遷移振幅を扱う方が多く、その方が断面積を計算するのに便利である。散乱振幅
Uij
に対する方程式を導こう。これは三つ巴の方程式から、直接導かれる。(3。14)式から、
(3.27)![]()
と定義できて、(3.25)式と(3.26)式を使えば、右辺は
(3.28)![]()
となる。定義(3.17)式と(3.20)式を用いれば、
(3.29)![]()
(3.30)![]()
更に、
(3.31)![]()
を得る。また、(3.29)式と(3.30)式から始れば、(3.24)式を用いて、
(3.32)![]()
(3.33)![]()
も求めることができる。これらは結合した方程式で、もっと簡単に書き表せば、
(3.34)![]()
となる。ここで、![]() 、また
、また ![]() の意味である。これを AGS
方程式と呼ぶ。
の意味である。これを AGS
方程式と呼ぶ。
Alt et al., Nucl. Phys. B2 (1967) 167.
実際には、3核子は同一粒子として扱うので、反対称化した状態を用いる。
(3.35)![]()
従って、![]() は粒子2と3に対して反対称であり、
は粒子2と3に対して反対称であり、![]() は1と3に対し、
は1と3に対し、![]() は1と2に対して反対称状態が仮定される。更に、粒子交換演算子
P
を使えば、明かに
は1と2に対して反対称状態が仮定される。更に、粒子交換演算子
P
を使えば、明かに
(3.36)![]()
(3.37)![]()
の関係を得る。従って物理的状態の![]() は
P
を使って、
は
P
を使って、
(3.38)![]()
と書表せる。この事は、(2.21)式で示した事と同じである。例として、終状態がチャンネル1になる散乱振幅 U1 を考えよう。定義から、
(3.39)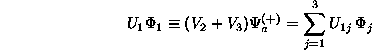
となり、チャンネル2と3に対する振幅(U2, U3)も同様に求まる。
(3.40)![]()
ここで、AGS 方程式(3.34)をそれぞれのチャンネルに対して、明らさまに書き直せば、
(3.41)![]()
となるから、Ui との関係(3.40)を使えば、
(3.42)![]()
(3.43)![]()
となる。ここで、もう一度 粒子交換演算子 P を使えば、
(3.44)![]()
(3.45)![]()
とできるので、あえて Ui に添字を付ける必要がなくなる。
(3.46)![]()
よって、(3.43)式は簡単になり、1つの式で書ける。
(3.47)![]()
この方程式は初期の段階では、2体の散乱マトリクス t を分離型にしたり、
(3.48)![]()
色々な技術を用いて解かれてきた。この場合、U は弾性散乱の振幅として次の様に書き表せる。
(3.49)![]()
次に、3つの粒子がバラバラに分解する場合を考えよう。漸近的な状態 ![]() は、自由なチャンネルだから、
は、自由なチャンネルだから、
(3.50)![]()
となり、明かに
(3.51)![]()
(3.52)![]()
に従う。また、散乱振幅 U0は
(3.53)![]()
で定義できるから、演算子 U0は
(3.54)![]()
と書けて、(3.24)式から(3.26)式の三つ巴を用いて、
(3.55)![]()
(3.56)
![]()
![]()
![]()
(3.57)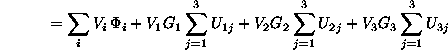
(3.58)![]()
(3.59)![]()
(3.60)![]()
最後の式で、又添字を省いた。ここで、U0は3粒子が分解するので、(3.60)の第1項のオエネルギー殻上に乗らない。従って、それからの寄与は全くなく、
(3.61)![]()
となる。
(3.62)![]()
のSchroedinger方程式から(3。53)式の定義は正しいことがを調べてみよう。
このブレイクアップのチャンネルに対しても、非斉次の項は考えられないことから、
(3.63)![]()
(3.64)![]()
と書ける。ここで、座標空間での3体自由グリーン関数は知られていて,
(L.S. Rodberg, R.M. Thaler, Introduction to the Quantum
Theory of Scattering, page 123)
(3.65)![]()
H2 はハンケル関数で、X
は
(3.66)![]()
により与えられる。漸近状態を調べるために、![]() と
と ![]() を∞にもって行けば、
を∞にもって行けば、
(3.67)![]()
で、更に、極座標を導入して
(3.68)![]()
(3.69)![]()
これより、
(3.70)![]()
と
(3.71)![]()
(3.72)![]()
(3.73)![]()
を使い、更に
(3.74)![]()
から、結局、
(3.75)
![]()
![]()
となる。ここで、p , q は
(3.76)![]()
(3.77)![]()
である。x, y を∞にもって行けば、明かに p ,q のヤコビ運動量と角度αによって決まる。また(3.75)式を(3.64)式に代入すれば、ブレイクアップの漸近的な形が分る。
(3.78)![]()
![]()
このことから、ブレイクアップの遷移振幅を読み取れる。
(3.79)![]()
完全に反対称的な![]() 状態は斉次な
LSE
方程式を満し、それ故、(3.54)式はブレイクアップの振幅であることが確認できる。
状態は斉次な
LSE
方程式を満し、それ故、(3.54)式はブレイクアップの振幅であることが確認できる。
さて、これらの2つの過程の振幅 ( U and U0 )を同一粒子の場合、まとめて書くと、
(3.80)![]()
(3.81)![]()
で、求められる。ここで、U を解く代りに次の量を定義すれば、
(3.82)![]()
(3.80)式は
(3.83)![]()
によって、解くことになり、この T を使えば、U とU0は、
(3.84)![]()
(3.85)![]()
で与えられる。
ここで、T は闇雲に導入した訳でなく、3体の
t
マトリックスとしての役割りを演じることを示そう。演算子
T
は定義から、![]() のチャンネルに働くので、明らさまに書けば、
のチャンネルに働くので、明らさまに書けば、
(3.86)![]()
これを、繰り返し代入していけば、
(3.87)![]()
これは、グラフで書けば、
(グラフ)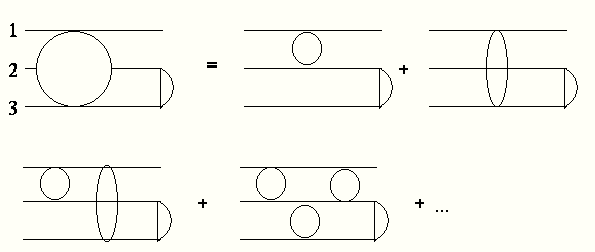
のようにより見透しの良い物理的な、メカニズムを説明する。ここで、積分核(t P G0 )において、 演算子 P により必ず異なるペアで t マトリックス結合することが、方程式を解けるものにしていることを数学的に示すことができる。(ここでは、深入りしない。)